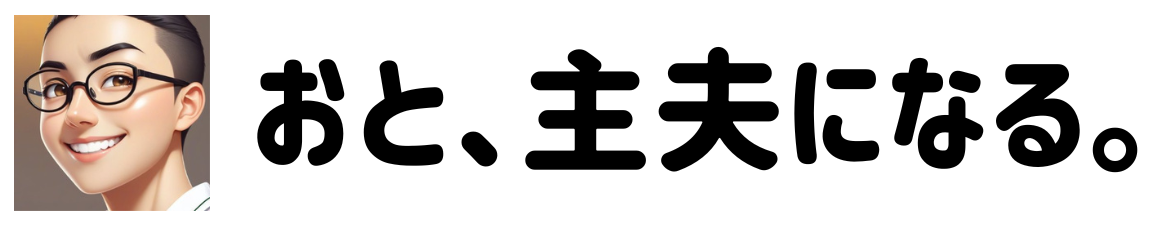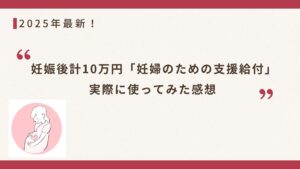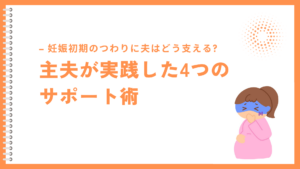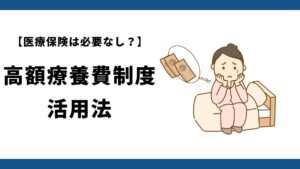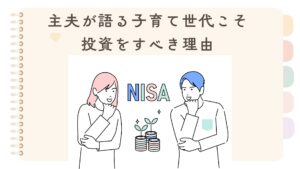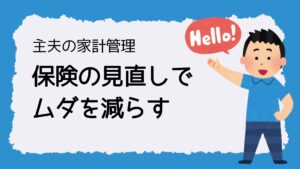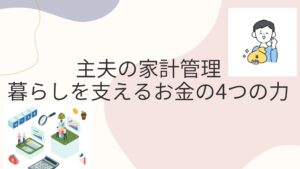【2025最新!】妊娠後計10万円「妊婦のための支援給付」とは?実際に使ってみた感想
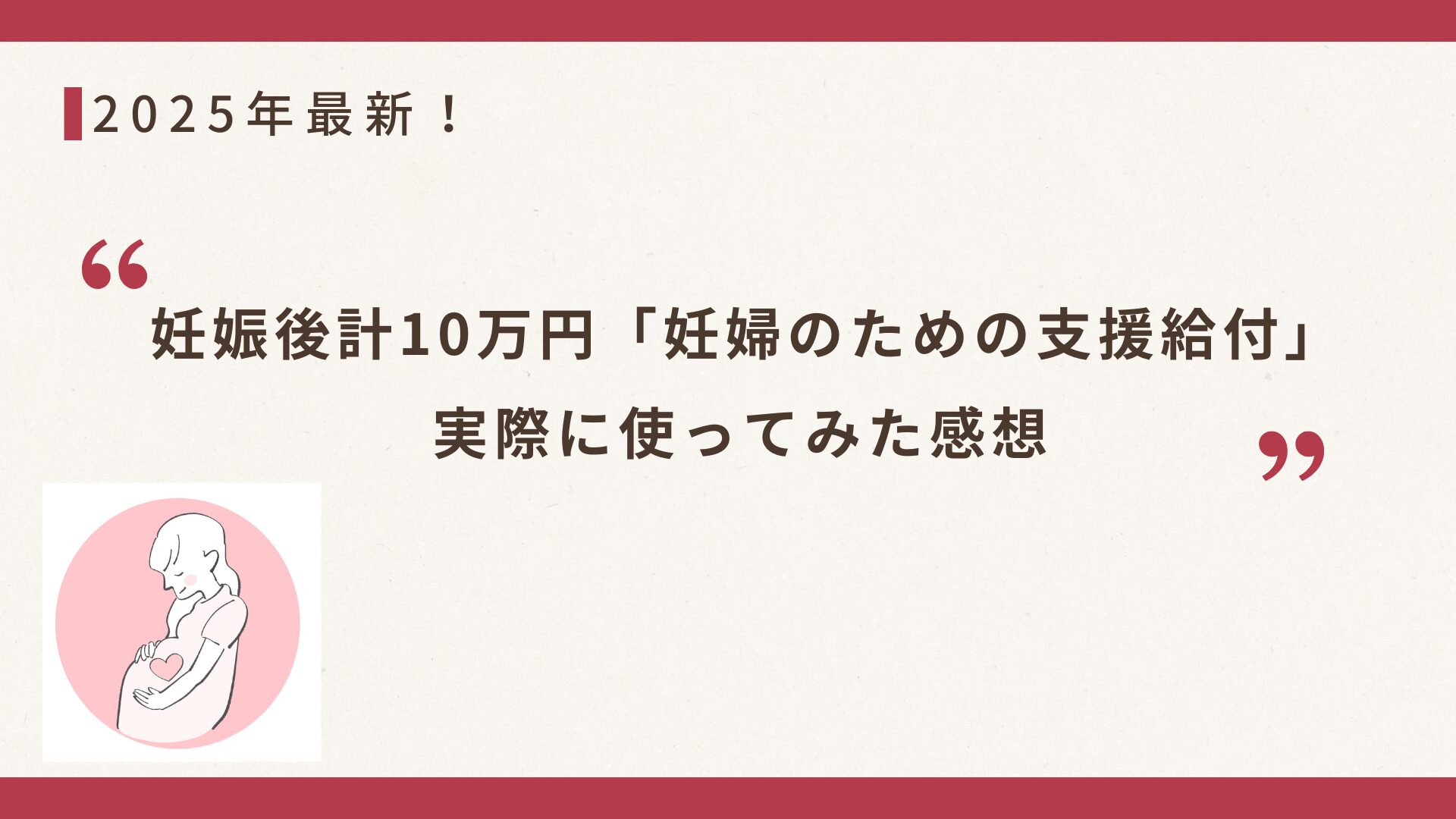
2025年4月から新たに、「妊婦のための支援給付」が始まりました。
皆さん、どんなものかご存じでしょうか?

私は妻が妊娠するまで知りませんでした!
2025年3月までは「出産・子育て応援交付金」として行われていたようですね。



新しく始まったみたいだけど、どうやって申請するの??
我が家は実際に先月申請し、
今月5万円給付されました。
また、出産前後に5万円給付され、
計10万円もらえることができます!
私が実践した簡単にできる給付金の受け取り方法を解説します!
この記事を読むメリットは、
・妊婦のための支援給付の内容がわかる
・申請方法や受け取り方法がわかる
・実際の体験談を知ることができる
上記3点を理解すると、簡単に受け取ることができますよ。
せっかくの給付金なので、
理解しておいて損はないです。
【妊婦のための支援給付】計10万円もらえる制度の概要
【妊婦のための支援給付】は
2025年4月(令和7年度)から始まりました。
これは、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から新たに作られました。
制度の概要は以下の通りです。
・対象者:申請時に妊娠している方
(母子手帳と一緒に申請することが多い)
・給付額:妊娠後に5万、
出産前後に5万の計10万円
→(出産前後は1人×5万円、
双子なら2人×5万円)
・相談支援が給付を受ける上で必要
→妊娠判明時、妊娠後期、出産後の3回
・アンケートや面談、
新生児訪問があることも



各自治体によって異なるので
注意してください。
実際に支援給付を申請してみた!
1、妊娠確定のため、医療機関へ受診
妊娠したかな?と思ったら、産婦人科を受診しましょう。
我が家は初めての受診が第5週のとき。



我が家は心拍が確認できた、
第8週で妊娠確定でした!
2.各自治体へ母子手帳の申請
産院から「次回から妊婦検診になるので、母子手帳を受け取ってきてください」と言われました。
申請方法は住んでいる自治体の役所や保健所に申請するのが一般的です。
ひょっとすると、電子申請が行える自治体もあるかもしれませんね。
私の自治体で、母子手帳の申請を行う上で必要だったものは、
・マイナンバーカード
だけでした!
自治体によっては病院が発行する「妊娠届出書」が必要です。
私の自治体では、
その場で自身で妊娠届出書を書きました。



ちなみに、申請は直接保健所に行くことをおすすめします!
「妊婦のための支援給付」申請も同時に行えるからです。
3.母子手帳と【妊婦のための支援給付】は同時申請でした
母子手帳の申請と同時に
がありました。
これらが【妊婦のための支援給付】の申請を行う上で必要なようです。
申請方法として案内されたのは、以下の2つ。
・紙に必要事項を記入して郵送
・QRコードを読み取っての申請
私たちは【QRコードを読み取っての申請】を選びました!
4.給付の電子申請、約5分で終わった!簡単!
自宅に帰ってからすぐに【妊婦のための支援給付】の申請を行いました。
QRコードを読み取り、必要事項を記入するだけ。
私の自治体は現金給付だったため、
【妻名義の口座情報】が必要でした。



申請から約1か月後、妻の口座に5万円入金されていました!
残り5万(産まれる人数×5万)は出産前後に
残り5万円(産まれる人数×5万)は自治体によりますが、出産前後に支給されます。
私の自治体では妊娠8か月頃にお知らせが届き、再度申請するようです。
クーポン券や地域通貨として給付されることも
自治体によっては、現金給付ではないところもあるようです。
一例として挙げられるものは以下の通りです。
・現物給付(ベビー用品、マタニティ用品など)
・電子マネー、クーポン
・地域通貨
・デジタルカタログギフト
【妊婦のための支援給付】を有効活用しよう!
2025年4月から新しく始まった
【妊婦のための支援給付】。
せっかく作られた制度ですので、忘れずに申請しましょうね。



給付金は
・マタニティ用品
・ベビー用品
など、赤ちゃんを迎え入れる準備に充てたいです!
意外とわからないお金の知識。まずは各自治体に問い合わせてみてくださいね。
参考資料
・育児年表でわかる子育て世帯がもらえるお金のすべて
著/高山一恵